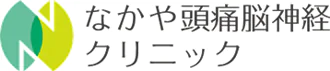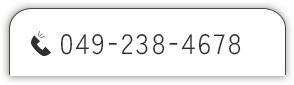頭頚部血管障害(脳卒中)による頭痛
脳卒中を含む脳の血管の病気による頭痛を説明します。
いつもの頭痛とは違って経験したことのないようなひどい頭痛が突然始まった!このような特徴がある場合には、もしかすると脳卒中が原因かも知れないと心配になります。この心配事をはっきりさせるためには脳内の血管を調べて、脳卒中の原因になりやすい脳血管奇形や脳動脈瘤といった血管の病気がないかどうかを調べてみるのがいいと思います。今でも多くの人が脳卒中になり、時には命に係わる危険な病気です。統計上では日本人の死因の第四位(厚生労働省 2021年人口動態統計より)に脳血管疾患がありこのほとんどが脳卒中になります。脳卒中の中でも代表的なものとしては血管が詰まることで起こる脳梗塞と血管から出血して起こる脳出血があります。中でも脳出血の時には強い頭痛とともに他の症状(麻痺や言語障害など)も見られることが多く、重症になってくると意識がもうろうとしたり意識が無くなったりしていてわかりづらいこともあります。
出血が原因となるもの以外には、未破裂血管奇形による頭痛や脳の血管の動脈炎によもの、頸部頸動脈または椎骨動脈の障害によるもの、頭蓋静脈障害によるものなどがあります。また、その他の急性頭蓋内動脈障害による頭痛や慢性頭蓋内血管症による頭痛、下垂体卒中による頭痛もこの分類に含まれています。今回はこれらを少し詳しく紹介するとともに、これに関連する病気についても紹介いたします。
脳梗塞による頭痛
脳の血管が詰まることで血の巡りがなくなった結果、脳に梗塞をおこすのが脳梗塞になります。梗塞が発生する範囲の小さい脳梗塞では多くの場合で頭痛は起こりづらいです。ある程度の太い血管が詰まって梗塞が発生すると麻痺が出たり言葉が出づらくなったりする症状とともに約1/3の患者で中等度の頭痛があるといわれています。
脳の血管が一時的に詰まったものの、早期に血液の流れが改善されて再度血が通うようになり梗塞を起こさない病気があり、これを一過性脳虚血発作(TIA)といいます。このTIAに伴う頭痛の場合では一時的な脳虚血発作とともに頭痛が起こるも24時間以内に消失する特徴があります。
脳出血による頭痛
脳梗塞とは違って脳の血管が裂けるなどにより脳内へ血が流れ出る病気が脳内出血です。出血がくも膜下腔という場所に発生するものはくも膜下出血になります。どちらの病気でも出血により脳内に血の塊ができるので、その刺激によって頭痛が引き起こされます。ほとんどの場合で突然の酷い頭痛の原因になります。出血の起こる脳の部分によって頭痛以外にみられる症状が異なります。麻痺が出たり言葉が話せなくなったりもしますが、酷い場合は意識障害が発生し命にかかわることもあります。出血の原因がどのような病気によるものかを調べたうえで緊急の治療が必要となることが多いので救急で病院にかかることを心がけてください。
脳動脈瘤の破裂または解離性動脈瘤の破裂によるくも膜下出血は恐ろしく、出血が起こった時にはすでに危篤となっている場合もあります。救急搬送で病院にたどり着いても治療を行えないくらい状態が悪い場合や何とか治療を行っても重度な障害が残ったり死亡してしまう病気です。統計的なデータとしては死亡率は40~50%であり、治療により一命を取り留めた人でも約半数の人に障害が残ります。
脳全体を包むように頭蓋骨と脳実質の間にある膜に硬膜というものがあります。この膜と脳自体との間に怪我や血管障害によって出血して血がたまってくる病気に急性硬膜下血腫というものがあります。これもひどい頭痛の原因になるのですが、血の溜まる量(血腫)によっては脳自体を押し付けてしまって麻痺の原因や意識障害の原因になります。ひどい場合は緊急手術によりこの血腫を取り除く必要があります。
これらのような頭蓋内の出血による病気を経験した後に頭痛が長引いて起こる人がいます。3か月以上にわたって頭痛があるときには持続性頭痛と診断します。どのような種類の頭痛が続いているかによりますが、基本的には内服薬により痛みを抑えることになります。
未破裂血管奇形による頭痛
脳自体を栄養している血管にも通常は認められないような異常が発生してこれが原因で頭痛が引き起こされこともあります。血管の異常には生まれつき存在していたもの(先天性)と年を取るにつれて出来てきたもの(後天性)があります。未破裂脳動脈瘤は後天性であることが多く、脳動静脈奇形(AVM)や海綿状血管腫(CA)はどちらかというと先天性であるとされます。未破裂脳動脈瘤は小さいものではあまり症状を出しませんが、大きなものだと脳神経の麻痺を生じることもあります。特に突然片方の瞼が開けづらくなり、痛みも感じるようであると動脈瘤がどんどん大きくなってきていて緊急性のある状態の可能性があります。AVMは脳卒中の原因にもなる病気ですが時にはけいれん発作で見つかることもあります。できている場所や大きさにより症状や治療の難易度が決まります。後頭葉に発生している方に片頭痛発作と同様の頭痛を持っている人が多いとされます。このような人の場合はAVMの治療をすることで頭痛も改善してきます。他には硬膜動静脈瘻(dural AVF)や海綿状血管腫、スタージウェィバー症候群という病気も頭痛の原因になるとされています。
動脈炎による頭痛
脳の血管に炎症が起こる動脈炎によっても頭痛は発生します。特殊な病気なのですが、巨細胞性動脈炎によるものや中枢神経原発性血管炎(PACNS)、中枢神経系続発性血管炎(SACNS)というものがあります。これらの病気になっている人の多くは頭痛を持っています。
頸部頸動脈または椎骨動脈の障害による頭痛
脳に血液を送り込んでいる血管には頸動脈と椎骨動脈があります。頸動脈は前方で椎骨動脈は後方で頸椎部の椎骨にある専用の穴を通っています。これらの動脈は首のあたりで何か異常があるとそのまま頭痛として感じることがあります。血管の異常が直接痛みにつながる場合と間接的に生じている場合がありますので、治療をするためには区別する必要があります。
この病気の中でも怖いのは動脈の血管の壁が裂けて起こる解離によるものです。血管の壁が裂けることで血液の通る内腔部分が狭くなることが多いです。それにより血液の流れが悪くなることがあるのと血管が裂けることで血管自体が膨らむのでこれが神経に触って傷害の原因になる場合があります。もちろん血管が裂けることで出血を起こすこともあります。血管が裂ける場合はある程度の部分にとどまることが多いです。そのために検査で異常な場所が見つかると、それを治すためにカテーテルを使った血管内治療や外科的手術を検討します。
頸動脈が脳を栄養する内頚動脈に分かれる分岐部に動脈硬化によってできる血管のプラークが大きくなって、血管の内腔が細くなることがあります。これがひどくなると脳梗塞の原因になることから、外科的手術によって血管のプラークの部分を切り取るか、血管内治療によりステント留置などで血管自体を広げる治療が行われています。これらの治療により脳梗塞の危険性は低くなるのですが、治療自体が血管への刺激になり頭痛の原因になることがあります。この頭痛が出るのは治療のすぐ後くらいからしばらくの間で自然に治まってくることがほとんどです。
頭蓋静脈障害による頭痛
頭痛の原因には動脈の異常だけではなく静脈の異常に関係したものもあります。脳を栄養した血液が心臓へと戻る際に通るのが静脈ですが、この中に血の塊(血栓)が出来てしまい血液の流れが悪くなる病気があり脳静脈血栓症(CVT)といいます。血液の戻りが悪くなることで圧がかかるようになり、その影響が脳内の圧にも影響してきます。どの部分に発生しているかにもよりますが、多くの場合は全体に圧がかかるためか頭痛自体は頭全体の痛みになります。段々とひどくなってくるので、頭痛に加えて頭蓋内圧亢進のような他の症状も見られるようになります。根本的な治療を行わないと頭痛だけではなくそのほかの症状も治らないので病院での治療が急がれます。
治療の手段として頭蓋静脈洞に血液の流れを良くするためにステント留置術をすることがあります。動脈の時と同じでこのステント留置をすること自体が頭痛の原因になることがあります。治療の後からしばらくの間は痛みが続くのですが次第に治まってきます。
その他の急性頭蓋内動脈障害による頭痛
脳外科領域の治療の進歩もあり、特にカテーテルを用いた血管内治療が進んだことで治療の手段が増えて脳卒中だけではなく他の病気にも治療が行えるようになってきました。それに伴い、治療の刺激が影響することによる頭痛も見られるようになりました。また、カテーテルの検査を行う際に使う造影剤での頭痛も認められています。これらの頭痛は一時的なものがほとんどです。
可逆性脳血管攣縮症候群(かぎゃくせいのうけっかんれんしゅくしょうこうぐん、RCVS: Reversible cerebral vasoconstriction syndrome)という病気があります。雷鳴頭痛でも説明いたしましたが、この病気の場合には何らかの理由で脳の血管が縮こまってしまう攣縮(れんしゅく)をおこすことで頭痛が起きます。脳血管攣縮はくも膜下出血を起こした人に見られる特徴的ものなのですが、RCVSの場合はくも膜下出血の時とは違って一時的で血管も元に戻る病気です。ただし、これによる頭痛は突然にひどい頭痛が起こる雷鳴頭痛として見られることが多く、頭部の画像検査でも初めの一週間くらいは異常がわからない場合もあります。最終的には頭部画像の脳血管の状態で診断するのですが、原因はよくわかっていません。痛みが起こる切っ掛けは性行為や労作、息こらえ、入浴、排便、感情の高まりなどの後に突然頭痛が始まりしばらくの間続きます。痛みが起こると咳をしたりシャワーを浴びたりすると同じような頭痛が起こるようになります。治療方法としては薬による経過観察になるのですが、時にはRCVSに引き続き脳卒中を起こす場合もあるので症状の変化に注意が必要です。
脳の血管の動脈が解離してしまい、これによる頭痛もみられます。画像診断の結果としてはRCVSに似ていることがあるものの、解離の場合は一部の血管に認められるので検査を繰り返していくことではっきりしてきます。血管の内腔が狭くなっていたり、出血したりしていると緊急での治療が必要です。
慢性頭蓋内血管症による頭痛あるいは片頭痛様前兆
とても稀な病気ではありますが、皮質下梗塞および白質脳症を伴った常染色体優勢脳動脈症(CADASIL)という病気やミトコンドリア脳症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作症候群(MELAS)、もやもや血管症によっても頭痛が生じます。また、高齢者の認知症に関係する脳アミロイド血管症(CAA)や脳白質脳症及び全身症状を伴った網膜血管症(RVCLSM)症候群といった病気でも片頭痛の様な頭痛が生じることがあります。
下垂体卒中
脳下垂体という部分に発生した脳卒中です。脳下垂体は成長ホルモンや女性ホルモンなどを分泌する部分でトルコ鞍という部分に納まる形で存在します。ここの部分に出血などの脳卒中が起こることでひどい頭痛が起こります。また、下垂体の腫瘍がある方でも出血する場合があります。視神経が近くに通っていることから出血がひどくて影響が及んでしまうと目が見えづらくなる症状が出ます。早期に診断して治療を要するので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか?
今回は脳卒中を含めた血管障害による頭痛を取り上げました。病気の種類はいろいろとありますが、頭痛の性質としては突然に起こるひどい頭痛であることが多く、早期の頭部検査が必要であることからこの点に注意していただけると幸いです。